
畜産DXが今、注目される理由
畜産業界は今、大きな転換期を迎えています。人手不足や高齢化という課題に直面する中、デジタル技術を活用した「畜産DX」が救世主として脚光を浴びているのです。
獣医師の地域偏在や過重労働、夜間対応の難しさ、書類手続きの煩雑さ—。これらの問題は、長年畜産農家を悩ませてきました。しかし、DXによってこれらの課題を一気に解決できる可能性が見えてきたのです。
特に2025年5月現在、大動物オンライン診療サービスの解禁により、畜産DXの動きは加速しています。遠隔地で薬が手に入らないといった事態にも対応できるようになり、畜産農家の負担は大きく軽減されつつあります。
では、このようなDX化を進めるための補助金制度はどうなっているのでしょうか?
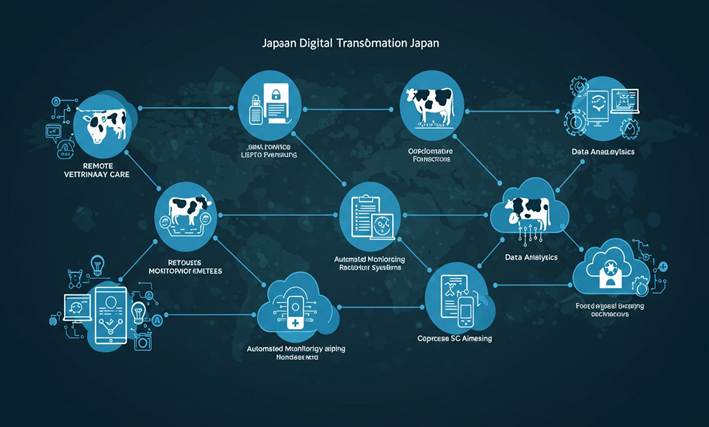
畜産DX補助金の種類と特徴
畜産DXを推進するための補助金は、国と自治体の両方から提供されています。それぞれの特徴を見ていきましょう。
国が主管する補助金制度
まず注目すべきは「中小企業省力化投資補助金」です。この補助金は人手不足に悩む中小企業等の省力化投資を支援するもので、2025年5月現在も申請を受け付けています。「カタログ注文型」と「一般型」の2つの類型があり、最大1億円の補助が受けられる可能性があります。
畜産業においては、飼料タンク残量の遠隔監視システムや家畜の健康モニタリングAIなど、DX技術の導入に活用できます。
次に「事業再構築補助金」も見逃せません。畜産業からDXを活用した新分野展開や業態転換を行う場合に申請可能です。例えば、オンライン診療と組み合わせたデータ分析サービスの立ち上げなどが対象となります。
「ものづくり補助金」も畜産DXに活用できます。生産プロセスの改善を目的とした設備投資等を支援するもので、農業用ドローンの導入などが対象となります。ただし、農事組合法人や農業協同組合は対象外なので注意が必要です。
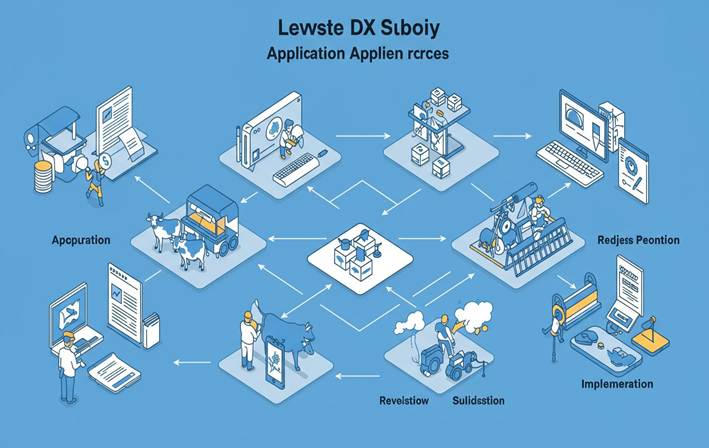
自治体が主管する補助金制度
各自治体でも畜産DXを支援する独自の補助金制度を設けています。例えば、新潟市の「農業DX・SDGsモデル事業補助金」や岡崎市の「新技術・農力向上プロジェクト事業費補助金」などがあります。
地域によって支援内容や金額は異なりますが、地元の特性に合わせた支援が受けられるのが魅力です。小規模な畜産農家でも申請しやすい制度も多いので、地元の農政課や畜産課に問い合わせてみるとよいでしょう。
自治体の補助金は国の補助金と併用できるケースもあります。賢く組み合わせることで、より効果的な支援を受けられる可能性があります。
畜産DXで実現できること
補助金を活用して畜産DXを導入すると、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか?
オンライン診療による獣医師負担軽減
大動物オンライン診療サービスの導入により、獣医師の移動時間が大幅に削減されます。緊急性の低い軽症や健康相談は遠隔で対応できるようになり、獣医師の負担が軽減されるのです。
夜間や休診日でも相談可能なオンライン窓口を設置できれば、農家の精神的負担も軽減されます。早めに相談することで、病気の悪化を防止できるというメリットもあります。
実際に宮崎県の畜産農家では、月に12回行っていた飼料タンク残量確認が月1回に減少した事例があります。これにより、人件費の削減だけでなく、突発的な注文もなくなり、配送費も低減できたそうです。

データ活用による生産性向上
畜産DXでは、家畜の健康モニタリングAIやセンサー・カメラによる行動解析が可能になります。これにより、発情・分娩の自動検知や異常の早期発見ができるようになるのです。
キリシマドリームファーム株式会社では、ITによる飼料管理を導入し、餌切れや突発注文がなくなりました。飼料タンクの残量を遠隔監視することで、効率的な飼料管理が実現したのです。
さらに、診療データの蓄積・AI解析により、疾病発生の予測と予防も可能になります。これにより、家畜の健康状態が向上し、生産性アップにつながるのです。
書類・手続きのDX化による効率化
畜産業では、さまざまな書類作成や手続きが必要です。これらをDX化することで、大幅な効率化が図れます。
診療記録・報告書の電子化により、紙カルテが不要になり、転記作業も削減できます。ワクチン接種・検査記録のデジタル管理も可能になり、情報の一元管理ができるようになるのです。
共済・補助金申請のオンライン対応も進んでいます。農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用すれば、オンラインで各種申請が可能です。家畜個体識別のデータ管理・提出も効率化され、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
畜産DX補助金の申請ステップ
畜産DX補助金を活用するためには、正しい申請手続きが必要です。ここでは、申請から導入までのステップを解説します。
事前準備と計画立案
まず、自社の課題を明確にしましょう。獣医師の負担軽減なのか、生産性向上なのか、書類手続きの効率化なのか—目的によって最適な補助金が異なります。
次に、導入したいDX技術を具体化します。オンライン診療システム、センサー・モニタリング機器、データ管理ソフトウェアなど、具体的な製品やサービスを検討しましょう。
そして、複数の補助金制度を比較検討します。国の補助金と自治体の補助金を組み合わせることで、より効果的な支援が受けられる可能性があります。

申請書類の作成と提出
補助金申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。これは、電子申請に必須のIDなので、早めに取得手続きを行いましょう。
申請書類は、事業計画書や収支計画書、見積書などが基本です。特に事業計画書では、DX導入による具体的な効果を数値で示すことが重要です。例えば、「獣医師の移動時間が○%削減される」「生産性が○%向上する」といった具体的な数値目標を設定しましょう。
書類作成が難しい場合は、専門家のサポートを受けることも検討してください。中小企業診断士や行政書士、ITコンサルタントなど、補助金申請に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。
審査と導入後のフォローアップ
申請後は審査があります。審査期間は補助金によって異なりますが、1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。
採択されたら、計画に沿ってDX技術を導入します。導入後は、効果測定を行い、必要に応じて改善を図りましょう。補助金によっては、定期的な報告が必要な場合もあります。
また、導入したDX技術を最大限に活用するためには、従業員の教育・研修も重要です。使い方を十分に理解し、日常業務に定着させることで、真の効果が発揮されるのです。
成功事例に学ぶ畜産DX活用のポイント
最後に、畜産DXを成功させるためのポイントを、実際の事例から学んでみましょう。
段階的な導入と従業員教育
DX技術は一度にすべてを導入するのではなく、段階的に進めることが重要です。まずは最も効果が出やすい部分から始め、徐々に範囲を広げていくとよいでしょう。
キリシマドリームファーム株式会社では、まず飼料タンクの遠隔監視システムを導入し、その効果を確認した上で、他の業務のDX化を進めていきました。このように、小さな成功体験を積み重ねることが、DX推進のカギとなります。
また、従業員の理解と協力も不可欠です。新しい技術に対する抵抗感を減らすために、丁寧な説明と研修を行いましょう。実際の業務でどのようにDX技術を活用するのか、具体的なイメージを共有することが大切です。
専門家との連携と継続的な改善
DX導入には、IT技術と畜産業の両方に精通した専門家との連携が効果的です。地域の農業改良普及センターやIT企業、大学などと協力することで、より効果的なDX化が実現できます。
導入後も、定期的に効果を検証し、必要に応じて改善を図ることが重要です。DX技術は日々進化しているため、常に最新の情報をキャッチアップし、システムをアップデートしていく姿勢が求められます。
畜産DXは、単なる業務効率化にとどまらず、アニマルウェルフェアの向上や環境負荷の低減など、多面的な効果をもたらします。補助金を賢く活用しながら、持続可能な畜産業の実現を目指しましょう。
まとめ:畜産DX補助金を活用した未来への投資
畜産DX補助金は、単なる設備投資の支援ではなく、畜産業の未来を切り開くための重要な投資です。獣医師の負担軽減、生産性向上、書類手続きの効率化など、さまざまな課題を解決する可能性を秘めています。
国や自治体が提供する補助金制度を賢く活用し、自社に最適なDX技術を導入することで、競争力の強化と持続可能な経営を実現しましょう。
申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、専門家のサポートを受けながら、一歩一歩進めていくことが大切です。成功事例に学びながら、自社に合ったDX化を推進していきましょう。
畜産DXは、これからの畜産業に不可欠な要素となります。今こそ、補助金を活用して、未来への投資を始める時です。
あなたの畜産経営が、DXによってさらに発展することを願っています。